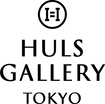作り手の声:陶芸家 木村展之さん(JP ONLY)
HULS Gallery Tokyoにて2023年6月9日から22日まで開催された、陶芸家 木村展之さんの作品展『青瓷と天目の世界』。木村さんは京都五条坂の陶芸一家に生まれ育ち、独立以前より取り組んできた青瓷に加え、近年では天目の研究にも力を注いでいます。今回の企画展に合わせて、作品の見どころやご自身の制作活動についてお話を伺いました。
- はじめに、陶芸家になったきっかけを教えてください。
祖父が絵付け職人、父が陶芸家なので、陶芸はとても身近な存在でした。母は古美術商の娘で、骨董品もよく見せてもらっていました。そういう環境で育って、ほかに特別やってみたい仕事があったわけではなかったので、高校卒業後は陶芸の専門学校に進みました。京都には陶芸の専門学校が2つ、ろくろの学校と釉薬の学校があって、僕は両方に2年ずつ行かせてもらいました。当時はろくろの専門学校が日本に2つしかなかったので、京都の学校には全国から窯元の息子さんなどが集まってきていました。4年間でいろいろな人と知り合えたのはとてもよかったです。
ろくろの学校では、1年目に土ものの基礎、2年目に磁器を学びました。釉薬の学校も1年目は基礎で、釉薬がどうやってできるのか、原料は何なのかといったことを教えてもらいました。2年目は実習で、僕は青瓷を選びました。青瓷が好きだったのもありますが、父が少し青瓷をやっていたんです。その釉薬を自分の力で再現してみたくて。学校でコツなどを教えてもらったことは、大きな財産になりましたね。釉薬の仕組みがわかったので、原料の組み合わせを変えてテストして、いろいろな色を出すのが面白くて好きになりました。そうして青瓷作家になり、初期の作品は派手な青でしたが、段々と艶のない渋めのものに変化し、色の種類も黄や赤などが増えていきました。

- 青瓷でこだわっていることは何ですか。
色の質感ですね。今は簡単に色を出せる市販の釉薬がありますが、それだと深みのある色は出せません。昔は自然の素材を使って発色させていました。日本では、焼成時に松などを燃やした灰が素地に降りかかり、融けてガラス化したことが釉の始まりと言われています。僕の青瓷では天然灰を使っていますが、灰に含まれる不純物の作用でいろいろな色が現れ複雑に重なり合うことで、独特の質感が生まれます。
青瓷には名品がたくさんあります。例えば、台湾の故宮博物院にある汝窯青瓷はとても有名です。1000年も前の中国で作られていたものです。以前に展覧会で直接見ることができましたが、いくつか並んでいる中にびっくりするくらい素晴らしい作品があって、その場に立ち尽くしてしまいました。絹をまとっているかのような質感でした。今はこうした名品の成分などを科学的に分析できますから、今ある原料で少しでもその雰囲気に近づけたいという夢を持ってやっています。

- 天目に挑戦された経緯についてもお聞かせください。
伯父(木村盛和氏)が日本で天目を再現した第一人者のような存在だったので、天目にはずっと憧れを感じていましたが、尊敬する伯父と同じ世界に踏み込むのは畏れ多いという気持ちもありました。でもその伯父が亡くなったとき、調合表などが行方不明になり作り方の謎が解明できなくなってしまいました。それなら自分でやってみようと、天目に挑戦してみることにしたんです。それが4年ほど前のことでした。ちょうど天目の研究者による講演会に参加したことやコロナ禍で外出しづらくなったことも、始める良いきっかけになりました。
- 実際に天目をやってみていかがですか。
楽しいです。焼き方が特殊で大変ですが、今まで憧れて見ていたものを自分で作れるようになったので。シンプルな油滴天目はすぐに出せたので、もっと面白い窯変を出したくて研究し、ブルーシルバーのような輝きの《鉄燿瑠璃光》ができました。

- これから挑戦してみたいことはありますか。
ずっとテストしているのは、油滴の斑点模様がドーナツ型になって現れる天目です。僕の師匠である清水卯一さんが得意としていたもので、あるとき平置きのピースでテストしていたら偶然できて、「卯一先生のドーナツが出た!」と大喜びしました。でも、立体の器になると流れて輪が崩れてしまい難しくて。今回の作品展で初めて綺麗にできたものを出品しましたが、理想はもっと輝きのある《鉄燿瑠璃光》のようなブルーシルバーの輪。宝石感のあるドーナツ型の天目を目指したいです。

木村展之さんコレクションページ:
https://store.hulsgallerytokyo.com/collections/nobuyukikimura