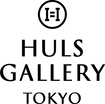作り手の声:ガラス作家 関野ゆうこさん(JP ONLY)
HULS Gallery Tokyoにて2025年10月10日から25日まで開催中の、関野ゆうこ作品展『うたかたの光』。東京での初個展となる本展では、泡の表情が織りなすガラスならではの景色が広がります。柔らかくも凛とした佇まいを見せる作品の数々について、作家の関野さんにお話を伺いました。
- 関野さんの作品の特徴と、今回の展示に向けて意識されたことを教えてください。
私の作品の特徴はやっぱり、表面の泡のテクスチャーや表情ですね。「うたかた(泡沫)」という言葉の柔らかい響きと実際のテクスチャーがマッチすると思い、シリーズ名にもしています。

また、泡を閉じ込める《沫のおもり》や《沫の盃》は、外側に泡をまとわせる《うたかた》とは異なる表情になります。制作過程のどのタイミングで作り出すかによって変化する泡を、感覚を大切に制作しています。

HULSさんは、日本文化に根付いた酒器や茶器を多く扱い、文化と工芸をつなぐ活動をされている印象がありました。そこで、本展では酒器や茶器、蓋物などの日本の器を意識して制作しました。打ち合わせでご要望があったお皿も新たに制作しています。

お酒はその時を楽しむもの、泡は弾けて終わるもの。そんな儚さの点で、お酒と泡はつながる気がします。お茶碗については、お茶を点てたときに立つ泡と器の泡が呼応するような景色を思い描いて作っています。

- 泡の表現を始めたきっかけを教えてください。
高校ではビジュアルデザインを学びましたが、平面よりも質感を出すことに惹かれていました。卒業制作では、照明のデザイン会社を想定して、照明・パッケージ・ポスターを作って総合的に完成させるという課題をやったのですが、照明を作ることにもすごく興味がありました。だから、ものづくりとテクスチャーと素材というのは、高校生の時からずっと自分の中にあったんだと思います。
- 素材としてガラスを選ばれたのはなぜですか。
ガラスはもともと好きでしたが、高校時代にイタリア研修へ行ける機会があって、その時に教会や美術館で見たステンドグラスやベネチアングラスにすごく惹かれたんです。自由時間にはガラスの展示ばかり見ていましたね(笑)。その頃から「自分はガラスが本当に好きなんだ」と自覚しました。大学進学の際にはガラスとプロダクトデザインどちらに進むか悩みましたが、ガラスを選ばなかったらきっと後悔すると思って、ガラスの道に進みました。
ただ美しいだけでなく、自分の作家性やガラスという素材の文化的・工芸的背景を表現したいと思っています。でも、日本において考えると、やっぱり陶芸にはかなわないんですよね。もともと工場での瓶づくりから始まっていて、工芸素材としての歴史はまだ浅いんです。
- 以前、陶磁器への憧れがあるとおっしゃっていましたね。
歴史的・文化的背景への憧れもありますし、初めての展覧会で、陶器と比べて「ガラスは綺麗でなければならない」という固定観念を強く感じたんです。「黒い部分※は何?」と尋ねられたこともありました。陶器なら“味”になる部分が、ガラスではそうは見られない。これは汚い、これは美人、みたいな(笑)。
綺麗な素材なのでその美しさは引き出したいんですけど、プラスアルファで“味”とも言えるような、無作為な表情を作品に取り入れたいと思っています。陶器への劣等感みたいなものがあったから余計に。そこからガラっと作風が変わりました。
※色ガラスの原料に含まれていた鉄分が、黒い点として残ってしまうことがある。原料の段階で完全に取り除くのは困難。

- 当時は現在とは異なる作風だったのですか。
大学ではアート工芸寄りの制作が主流でした。使えないものでも、「大きいものを作ろう、素材で何かを表現しよう」という気風がありました。でも日本では、そういう工芸を多くの方がご自身の生活の中に取り入れるって難しいですよね。大きな家やホテルだと大きなアート工芸作品が飾れるかもしれないし、アメリカなどはグラスアートのマーケットが確立されているから、大きい作品を作ることに対しての需要があります。ところが日本の工芸ってなんだろうって考えたら、私はやっぱり「使えるもの」を作りたいと思ったんです。だから、大学での作風からは方向転換して、「使えるもの」としての工芸を意識しながら、泡や金属の化学反応といった新しい表現を模索してきました。テクスチャーだけじゃなく、素材と形とを考えながら。
- 金属との化学反応を活用した作品について教えてください。
銅箔を使ったのが、《蒼のうたかた》と《蒼の重なり》のシリーズです。熱いガラスに銅箔を巻き付けると、化学変化によって銅が青く発色します。黒くなっているところは、箔の重なり合っている部分や、しわになっている部分。そういうところも表情としてすごく好きなんです。

- 新作《銀漢》シリーズが誕生した経緯を教えてください。
黒も挑戦したいなと思ったんですよね。黒いガラスと銀の組み合わせが面白いなと思いながら、テストピースにサンドブラストを当てたり、ガラスに銀の粒を癒着させてみたり。《うたかた》のテクスチャーの上だと、銀の粒が取れてしまうことがあるんですけど、その表情はすごく素敵だったので、なんとか取れないように工程を工夫しながら実験を重ねました。そういうのがすごく楽しいんですよね。
最初は茶箱に入るような小さい蓋物を作りました。このテクスチャーがすごく合いそうだなと思って。

- 自信作や注目してほしい作品はありますか。
《蒼のうたかた》の大きな花器です。筋力の問題で、大きな作品を作るのは女性には難しいんですよね。重たい(笑)。大きな作品が主流のアメリカでは、マッチョな男性が3~4人で協力して作ったりしています。この作品は同じくガラス作家である夫の助けも借りながら作りました。バランス良く仕上がったと思います。

あと、《うたかたに満ちて》《蒼きうたかたに満ちて》の花器も見ていただけたら嬉しいな。表面張力を意識して制作したもので、水があふれ出しそうな現象をガラスで表現しています。

- 最後に、お客様へのメッセージをお願いします。
一つひとつの泡の表情や箔の重なりの違いを見ていただけるのは、展覧会ならではだと思います。私は、形は技術でコントロールするものと思っているんですが、泡の表情や箔の重なりはコントロールできない部分。そういう部分をお客様に見ていただき、気に入ったものを選んでいただけると嬉しいですね。
関野ゆうこさんコレクションページ:
https://store.hulsgallerytokyo.com/collections/yukosekino