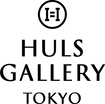作り手の声:眞窯 加藤真雪さん(JP ONLY)
HULS Gallery Tokyoにて2025年6月13日から28日まで開催された眞窯 加藤真雪 染付展『Blooming in Blue』。瀬戸染付焼の窯元「眞窯」の四代目である加藤真雪さんは、伝統的な技法を受け継ぎながら、現代的な感性で花々を繊細に表現した作品を生み出しています。今回の企画展に合わせて、制作の背景や作品の見どころについてお話を伺いました。
- HULS Galleryでは初めての展示ですが、ご自身の中で意識されたことはありますか。
HULS Galleryでは以前から眞窯の作品を取り扱っていただいていて、雰囲気がすごく合うなと感じていました。今回は無釉薬の白地に花を描いた私の作品が中心で、いろいろな花の魅力に触れてもらえたらと絵柄のバリエーションを多く用意しました。無釉薬の染付は、釉薬を掛けないとどうなるのか試してみたところ焼き上がりの雰囲気が良く、それからずっと作り続けています。ほかではあまり見たことがない風合いで、日常の中に取り入れたら背筋が伸びるような特別な時間を作っていただける気がしているので、この展示でもっと広く知ってもらえたらいいなと思っています。

- 最初に、瀬戸染付焼について教えてください。
染付は白地に青く発色する呉須で描く技法のことですが、瀬戸染付焼が確立されたのは19世紀の初頭くらいと言われています。それまで瀬戸はずっと陶器を作ってきた産地でしたが、有田の磁器の人気に押されて需要が下降気味になる中、加藤民吉さんという方が九州へ磁器の製法を学びに行き瀬戸に持ち帰ったことで、磁器の生産が始まりました。こうした歴史があり、眞窯では磁器を作っていますが、瀬戸は磁器と陶器の両方を生産している珍しい産地で、染付についても磁器だけでなく陶器の染付が存在します。絵柄については、花鳥風月のモチーフで南画※1 風の写実的な表現が特徴と一般には言われていますが、今は現代の食卓に合ったものに変わってきています。瀬戸の土は他産地と比べて白く染付のブルーが鮮やかなので、私たちはその色合いを活かしたくて、白地を際立たせるようなシンプルなデザインが多くなっています。瀬戸染付焼は伝統工芸品に指定されていますが、守るだけでは未来に繋がっていかないので、技術やエッセンスを受け継ぎながら、今の生活に合ったデザインを提案していこうと取り組んでいます。
※1 南画…中国の南宗画に影響を受けて、江戸時代の日本で発展した絵画の一つ。山水や花鳥を水墨や淡彩で描いたものが多い。
- 今回は真雪さんの作品だけでなく窯元の人気作も出品いただいていますが、どのように区別しているのでしょうか。
窯の製品は、私、父、母のデザインがあり、《youmyaku》や《麻の葉》は父、《ライン》は母のデザインで、アップデートを重ねながら数十年作っているシリーズです。担当を分けて製作しているので、デザインした人が必ずしも作っているわけではありません。窯の製品と決めたもの以外は、私がデザインを考えて絵付けしています。

- さまざまな花のデザインは、いつ頃から始められたのですか。
花のモチーフはもともと母が手掛けていました。今とテイストは違いますが、小さい頃から母が絵付けするのを見ていた記憶があります。私も両親も眞窯らしいものを作りたいという思いがあり、その中で花のデザインも大胆に描いたり余白を持たせたり、他にはない表現を模索しながら変化してきました。
- 特にこだわっているところはありますか。
絵柄をどのように配置するかというところです。型の原型は自分たちで削って作っているので、形も含めた全体的なデザインを細かいところまでこだわることができます。構図はその花のどこが一番魅力的に感じるかということを意識していて、例えばスッと一本立っているような芯の通った感じがいいなと思ったら、あえて器の真ん中に配置することもあります。洋食器に多い華やかな絵付けや左右対称のデザインに憧れた時期もありましたが、今は海外のお客様が増えたこともあって、余白を持たせた日本らしい美しさを表現できたらいいなと思っています。

また、筆をスポイトのように使って絵の具を流し出す「濃み」は、紙や布ではできない、やきものの染付だけの技法なので大事にしています。花の表現にはぴったりで、花のシリーズは濃みだけで描いています。濃みが絵の具で線描きをした内側や外側を塗るという補助的なものでなく、主役になっている作品です。作品を通してこの技法にもスポットライトが当たり、興味を持ってもらえたら嬉しいです。

- 真雪さんの作品はマットな質感が特徴的ですが、どのように生まれたのでしょうか。
最初は器として使うものに釉薬を掛けないのはどうなのだろうと思っていたのですが、いろいろと試作を繰り返して、機能面とデザイン面のバランスが取れた今の形になりました。釉薬を掛けると焼いたときにどうしても絵の具が滲んだようになり、それはそれで良さがあるのですが、釉薬を掛けないと焼く前の状態に近い、細部がはっきりとした繊細な表現になります。小さな傷も全部見えてしまうので丁寧に仕上げなければならなくて手間は掛かるのですが、無釉薬だからこそ出せる表情がとても好きなので続けています。染付の技法はすでに確立されていて、始めた頃は表現として広がりがないように感じていましたが、釉薬の有無、釉薬と絵の具の組み合わせ、焼き方によって、同じ原料を使っていても全然違う色合いになるので、すごく面白いなと思います。他の窯元さんや作家さんの作品を見ていても、同じ白地に藍色の絵の具を使ったやきものでも多様性があって奥が深いなと。従来の形にとらわれすぎず、これからも新しい染付の表現方法を探っていきたいと思っています。
- 金彩や銀彩の装飾もアクセントになっていて素敵です。
金彩や銀彩は、従来の染付に自分らしさを加えたくて始めました。呉須の藍色と金銀の組み合わせが綺麗で、表情に変化が出ていいなと思っています。
- 新作や自信作はありますか。
絵変わりの小皿やグラスは、同じ柄がいくつもあるよりは違った柄を楽しみたいなと思い、やってみたかった作品です。海外のお客様も多いと聞いていたので、和の花を中心に描きました。

木蓮は以前から描いていますが、形状やサイズに合わせてデザインを考えました。桜は今年から始めたシリーズで、一輪挿しも新しいです。木蓮やハスのフラットプレートは飾っても楽しめますし、いろいろな使い方ができるのでおすすめです。

- 最後に、お客様へメッセージをお願いします。
器は使ってもらって完成すると思っていて、料理を載せたときや花を生けたときにどう見えるか考えながら作っています。最近はSNSなどでお客様が使っているところを見られるので、「こんなふうに使ってくれているんだ」という新しい発見や驚きがあって、お客様と一緒に作っている感覚があります。楽しんで使ってもらえたら嬉しいです。

眞窯コレクションページ:
https://store.hulsgallerytokyo.com/collections/shingama